【小説】幻庵(百田尚樹)
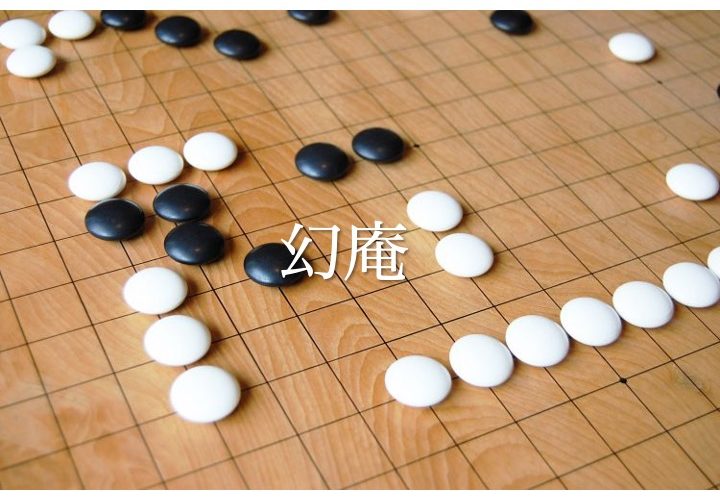
「永遠の零」で有名な百田尚樹さんの「幻庵(げんなん)」を読みました。
この本を手に取った理由
僕がこの本を読んだきっかけは本屋での立ち読みです。百田尚樹さんの「影法師」を以前読んで面白かったので、本屋に並んでいた「幻庵」も気になって冒頭だけ読んでみました。
プロローグとして囲碁の紹介があるんですが、これが個人的にすごく興味をひかれる内容でした。将棋やチェス、囲碁もいまやAIが人に勝ってしまうというのはなんとなく知っている人が多いですよね。ではいつ頃からAIの方が強くなったかというと、チェスは20年以上前のことらしい。ヨーロッパでは「人類の究極の知性」とか「キングオブゲームズ」とか言われるチェスの世界王者が1997年にAIに敗れ、世界に衝撃を与えたとのことでした。
じゃあ囲碁も1995年とか2000年くらいかなとなんとなく思ってしまうんですが、チェスから約20年後の2016年らしいです。ルールの説明は難しいので省きますが、囲碁は19×19の碁盤に1手目からどこでも好きなところに指してよいというかなり自由度の高いルールの中で、いかに自分の陣地を広げるかを競うゲームです。この自由度の高さが囲碁の面白さであり難しさでもあるようで、AIがチェスで世界王者を倒した1997年、囲碁ではアマチュア有段者にすら敵わなかったみたいです。
これを見てなんとなく「囲碁ってすごいんだな、奥深いんだろうな、気になるな」と思って、買っちゃいました。余談ですが漫画「ヒカルの碁」もかなり面白くてオススメです。
あらすじ
囲碁は紀元前1000年ごろ中国で誕生し、紀元前500年ごろにはほぼ今の囲碁に近いゲームになっていたそうですが、この本は江戸時代の日本の囲碁界を舞台とした話です。江戸後期は多くの天才が現れ、碁界最高権威の「名人碁所」をめぐって死闘を繰り広げた時代で、その中でも多くの人を魅了した「幻庵」と「丈和」の二人の天才を中心に描かれています。
※かなり昔の話ですが、囲碁では棋譜というのが残っていて、丈和が1手目にどこに打って、幻庵が次にどこに石を置いて、それを丈和がどう受けたといったように、江戸時代の棋士がどのような囲碁を打ったか、具体的にわかるようです。
二人の命をかけた戦いはもちろん、親友や師匠、弟子との絆も非常にグッとくるものがあり、楽しめると思います。
上巻・下巻あわせて800ページ以上あり、なかなかボリュームがありますが中盤からはページをめくる手が止まらなくなるアツい話です。囲碁が全然分からない人でも問題なく、楽しめると思います。上に書いた「命をかけた」って表現が大袈裟に感じる人もいるかと思いますが、読んでもらえればそうじゃないことがわかってもらえるはず。
感想
全体として面白いです。似た名前が多く出てきますし、○代目算知とかみたいに襲名していくかたちなのでややこしい部分もありますが、上巻の半分くらいまで読めば、それ以降は続きが気になって止まらなくなります。囲碁って正座して黙々と打つイメージだったのですが、読んでいくと全く印象が変わりました。
勝負する二人の気合がばちばちとぶつかりあうような激しいもので、入り込んで読むと、ボクシングを見てるような緊迫感があったり、サッカーの選手権の試合を見ているようなアツい気分になったりします。
幻庵と丈和ももちろん魅力的なのですが、それ以外にもたくさん魅力的で個性的な登場人物が出てきます。僕が特に好きになったのが「元丈」と「知得」でした。
「お互いに因果な身の上だな」知得は言った。
「まったくだ。物心つく前に碁を覚え、碁盤の上で白と黒の石を並べて一生を終えるのだからな」
「後悔してるのか」
「いや。後悔も何も、ほかになにもできんしな」元丈はそういって豪快に笑った。
「むしろ、こんなことで暮らしてゆけるなど、果報なものだと思う」
「俺もそう思う」と知得は言った。
(中略)
二人はしばらく黙って茶を飲んだ。やがて知得が呟くように呟くように言った。
「しかし、俺たちは何のために碁を打っているのだろうな」
「この技芸を高めるためじゃないか」
「碁打ちは魚をとるわけでもない。米を作るわけでもない。碁などなくなったところで誰も困らぬ。碁の技芸が高まることで、何かの役に立つのかな」
「俺は思うのだが-」元丈は言った。「三千年も昔に碁が生まれたということは、それだけで何かしら意味があるのだと思う。もしも碁と言うものが、その間に簡単に極め尽くされていたなら、今頃、碁打ちなどと言うものはどこにもいない」
「うむ」
「幾多の師が盤上の棋理を求めて精進されたが、今もなお、我らは碁の奥義の入り口に立てたかどうか-。もし、碁を極め尽くした仙人がいるならば、我らは彼に三子は置かねばならぬと思う」
知得は黙って頷いた。
「いずれは碁の仙人に二子に迫りたい。我らの代では無理かもしれぬが-」元丈は言った。
「百年後、いや二百年後の碁打ちならば、二子で打てるようになるやもしれぬ」
「俺たちはそのためにあるのか」
「そう言うことだ。だからこそ、後世のためにもいい碁譜を残さねばならぬ。俺たち碁打ちは、碁の棋理を極めるための捨て石の一つにすぎん。知得は、それでは不満か」
「いや」と知得は笑って答えた。
「大いに満足だ」
(P 231)
※○子置く=勝負する二人の力量に差がある場合にあらかじめ弱いほうがいくつか石を置くことでバランスをとること。いわゆるハンデ。
互いに切磋琢磨し、その時代の頂点を極めた元丈と知得のやりとりです。ほかにも紹介したいいいシーンはいくつもありますが、特に印象に残っているシーンのひとつです。名人を目指す上でのライバルでありながら親友でもある二人の仲の良さと優れた人格、囲碁に取り組む姿勢と情熱、何百年何千年かけても極め尽くすことができない囲碁というもの深さのわかる場面で、穏やかで微笑ましいシーンなのに鳥肌の立つ不思議に感覚を覚えました。
ネタバレになってもいけないのであまり詳しくは紹介できませんが、この本の主役である幻庵と丈和の二人も、元丈と知得のように互いを高め合うライバルではありますが全く雰囲気は違います。もっとばちばちとしていて、また違うかたちで楽しめます。
ボリュームがありますし、囲碁を知らない人にとってはなかなか手が出づらいかもしれませんが、誰でも楽しめるオススメの小説です。
-
前の記事

紫のトルコキキョウ 2020.06.20
-
次の記事

【小説】アーモンド(ソン・ウォンピョン) 2020.06.28



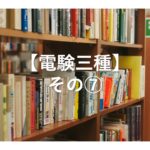


コメントを書く