【一級建築士】その①一級建築士資格の取得にチャレンジ
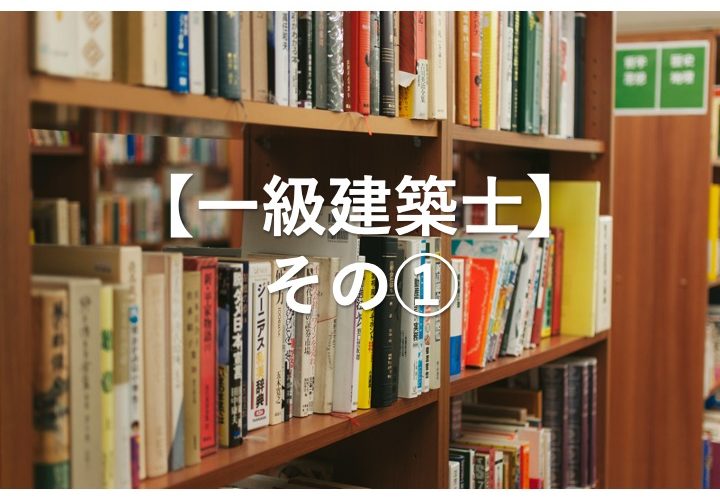
こんばんは。
2020年12月28日、無事一級建築士の合格通知書が届きましたので、合格するまでの体験をまとめたいと思います!
その①〜その⑥の全6編でお送りします!
その①:一級建築士資格の取得にチャレンジ
その②:学科試験1年目(失敗談)
その③:学科試験2年目(成功のポイント)
その④:設計製図試験1年目(失敗談)
その⑤:設計製図試験2年目(成功のポイント)
その⑥:一級建築士試験合格のため!
これから一級建築士を志す方、チャレンジ中でうまくいっていない方の参考になると嬉しいです。
それでは本編ではその①について書いていきます!
一級建築士試験の概要
そもそも一級建築士の資格を取得することで何が出来るようになるの?難易度は?試験の時期は?
そういった概要について、簡単にまとめます。
■一級建築士資格取得のメリット
・建設系の会社に勤める場合、昇格に必須だったり給料が上がったり。
・独立や転職に役立つ。
・規模の大きな建物の設計が出来るようになる。
■試験内容
・7月下旬に学科試験があり、学科試験を合格した人は10月中旬にある設計製図試験を受けることになります。
・学科試験(一次試験)は「計画」「構造」「施工」「設備」「法規」の5つの科目を受験し、全科目で約6割以上の点数を取った上で、全体合計として70〜75%程度の点数を取れば合格となります。
※この合格ラインはその年の試験の難易度によって変動します。
・設計製図試験(二次試験)は与えられた条件にあった建物を6時間半以内に設計し、図面にまとめる試験です。ランク1〜4で評価され、もっとも上のランク1と判断された人だけが合格となります。
・設計製図試験は一度学科試験に合格すれば3回チャレンジすることができます。
※令和元年までは、学科試験に受かった年に設計製図試験を受けることができ、その翌年、翌々年も学科試験なしで設計製図試験を受けることができた。
※法改正により令和2年以降の学科試験合格者は、合格後の5年間のうち3回好きな年に受けることが出来るようになった。
■難易度
・学科試験の合格率は15〜20%程度。
→10人に1〜2人しか受からないためなかなか競争率の高い試験かと思います。
・設計製図試験の合格率は30〜40%程度
→合格率だけ見るとそこまで難しくないように思えますが、厳しい学科試験を勝ち抜いた人たちの中で半分より上に入る必要があるため、実際は学科試験よりもかなり難しく、厳しい試験になります。また2年目・3年目の受験者もいるため、初受験の受験者にとっては特に厳しい戦いになります。
■受験資格
・令和元年までは大学の建築学科を指定の科目を修めて卒業し、実務経験を2年以上積めば受けることができた。
・令和2年からは大学の建築学科を指定の科目を修めて卒業すれば、すぐに受けることが出来るようになった。
※免許の発行には実務経験2年が必要。
■取得にかかる費用
・どの資格学校に通うかによって大きく異なるが、設計製図独学での合格はほぼ不可能なため、どんなに抑えても30万円。講座や教材が充実した資格学校に学科・製図ともに通えば、一発合格でも100万円以上かかります。
僕が勤務する会社の場合、建築設計や構造設計は昇格のために一級建築士の取得が必須となっています。ただ設備設計の場合、その他の資格でも代替出来るため必須ではなく、給料にも関わらないので取らなくても問題はないのですが、せっかく建築学科を卒業したんだし受けとくか!というかんじで受験しました。
僕が合格するまでの道
僕の場合、受けようと決めてから合格するまでに5年間かかりました…
2016年(実務経験不足で受験資格なし)
→総合資格の2年間コースを申し込み、11月から講座始まるも危機感なく通わず
2017年(実務経験不足で受験資格なし)
→講座開催されているが仕事が忙しいのと試験もまだ先だと思って通わず
2018年(この年から受験可能)
→準備開始がかなり遅れて勉強不足、若干点数足りず不合格
2019年(学科2回目のチャレンジ)
→学科合格!製図は単純に実力不足でランク4、不合格
2020年(製図2回目のチャレンジ)
→設計製図試験合格!
このあたりをその②以降で詳細に紹介していきます!
-
前の記事

年末年始の運動不足に!いま僕がハマっている足パカ体操! 2020.12.28
-
次の記事
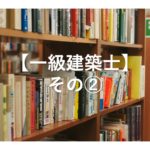
【一級建築士】その②学科試験1年目(失敗談) 2020.12.30
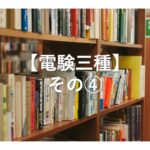



コメントを書く