【小説】わたしを離さないで(カズオ・イシグロ)
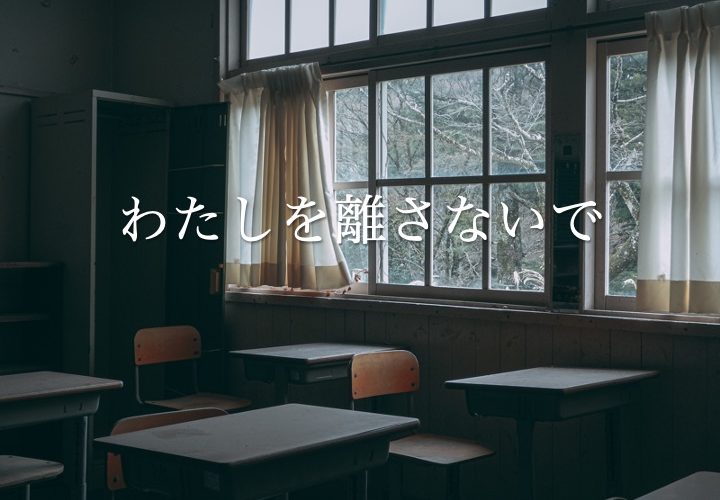
2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロさんが2005年に出版した小説。ノーベル文学賞を受賞した時には、本書の名前をよく目にしました。
「ノーベル文学賞」という格式高さゆえに、「読んでも理解できない難しい本なのでは…」とビビって今日まで手を出していなかったのですが、ツイッターでオススメしてもらい、今回初めて読みました。読んでみると、身構えていたような難しさはなく、小説が好きな方にはぜひ読んでもらいたい本だったので紹介させていただきます!
あらすじ(ネタバレなし)
主人公のキャシーは提供者を世話する介護人。物語はキャシーが自身の生まれ育った施設「ヘールシャム」での生活から現在までを回想することで進んでいきます。
ヘールシャムでの学生生活は、一見するとどこにでもありそうな生徒たちのやりとりで満ちていますが、物語が進むほど奇妙な点が浮き彫りになります。
図画工作に異常に力を入れた授業、毎週のように行われる健康診断、外界との関わりを断絶された施設。キャシーたち生徒が核心に近づく度に拒否感をあらわにする保護官。そして、彼女の回想はヘールシャムが存在する残酷な真実を明かしていきます。
理解しているようで、理解していない
謎に包まれたヘールシャムの生活で、キャシーは親友のルースやトミーと自分たちが感じる違和感の正体を知ろうともがきます。学年が上がるにつれて徐々に明かされる真実。しかしルーシー先生はトミーにこう言います「君たちは理解しているようで理解していない。」
読者もこの物語を読み進めていくと「理解できそうで理解できない」という感覚に陥ります。初めは、どこにでもある学生生活、どこにでもある生徒たちのやりとりです。しかし徐々に普通ではない“違和感”を随所に感じ始めます。分かりそうで分かりきらない絶妙なヒントを与えられながら、ヘールシャムで成長するキャシーたちとともに少しずつ明らかになっていく真実を知っていきます。全ての仕掛けが明らかになるのは物語の本当に最後。正確にいうと、全て読み終わっても、どこかに違和感が引っかかっているような感覚でした。
小説では珍しい「〜です/〜ます調」で書かれた文章に、少し読みづらさを感じましたが、この違和感もまた、物語そのものの違和感を際立たせている気がします。扱われている題材は重ためですが、物語自体は読みやすいです。不思議な世界観に浸りながら、精巧に書かれた本を楽しみたいという方は、ぜひ読んでみてください。
(以降はネタバレありなので、これから本書を読みたい方は見ないほうが良いかもしれません。)
日本の小説にはない世界観(ネタバレあり)
本書がもつ不思議な世界観は、今まで感じたことがない類のものでした。ヘールシャムで生活する生徒たちに明かされる真実は、物語の序盤に散りばめられている違和感をつなぎ合わせることで、もしかしてこういうことなのか?と読者に推測させます。でもこの真実が物語のクライマックスに明かされるだけではちょっと味気ないなぁ…と思いながら読み進めると、物語の3分の1にも満たない場面で突然真実が明らかにされます。生徒たちは、将来臓器提供を行うために生まれてきたと。
クローンを扱う小説はこれまで何冊か読んできましたが、本書が他と異なるのは臓器提供を目的としたクローンである事をミステリーのクライマックスとして使うのではなく、物語の比較的早い段階で明らかにしているところだと思います。真実を知ったキャシーと仲間たちが、自分たちの宿命について話し合い、時にその話題を避けながらも、何を思い、来るべき日に向けて生きて行くのかに焦点が当てられています。
小難しい解釈になってしまいますが、著者が本書で伝えたかったのは、遺伝子工学の発展に対する警鐘だと思います。物語の終盤に、キャシーとトミーに向けて投げかけられたこんな言葉がありましす。
癌は治るものと知ってしまった人に、どうやって忘れろと言えます?不治の病だった時代に戻ってくださいと言えます?そう、逆戻りはできないのです。
p401
臓器提供を目的とするクローンの存在が当たり前となった世界で、そのクローン本人たちが真実を知りながら生きて行く、その過程の感情を緻密に描く事で、「あなたたちはこの世界を正しいと思いますか?」と聞かれているような気がしました。
と、言いつつも、本書の真意を汲み取れたかと言われると、少々自信がないです。不思議な余韻を持った本でした。これはぜひ、すでに読んだ人と話し合いたい一冊です。
-
前の記事

【小説】ナミヤ雑貨店の奇蹟(東野圭吾) 2020.08.13
-
次の記事

【小説】ノースライト(横山秀夫) 2020.10.17


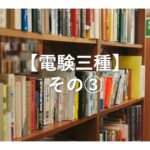

コメントを書く